インデックス付き
- レフシーク
- ハムダード大学
- エブスコ アリゾナ州
- パブロン
- ジュネーブ医学教育研究財団
- ユーロパブ
- Google スカラー
このページをシェアする
ジャーナルチラシ
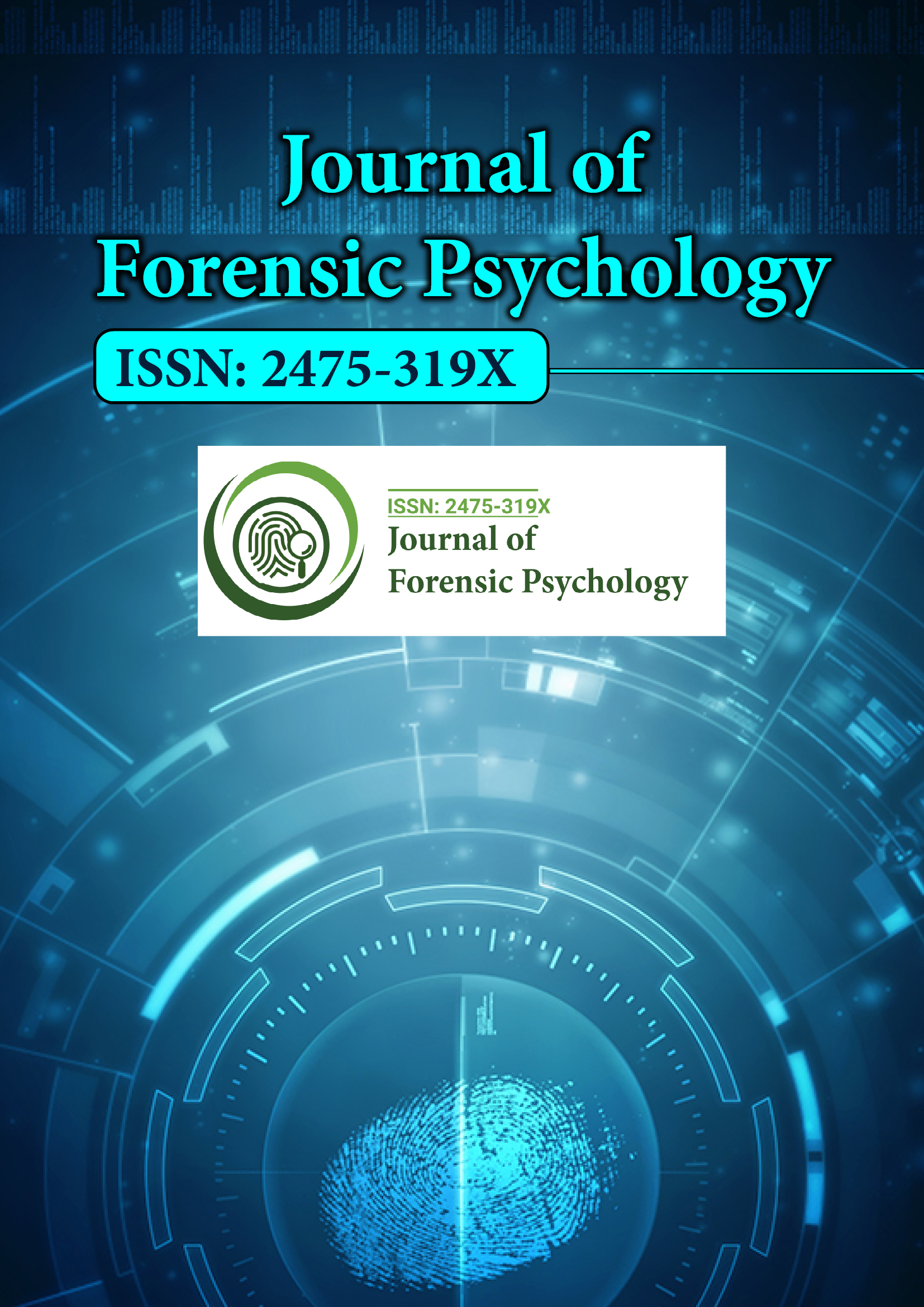
概要
保護観察所による知的障害のある犯罪者の監督:課題と問題点
マイク・ヘレンバッハ
背景:入手可能な証拠は限られているが、知的障害 (ID) を持つ犯罪者は保護観察対象者の中でかなりの少数派を構成していることを示唆している。しかし、保護観察官がこの集団を監督および管理する際に、競合する構造的要求をどのように調整するかについてはほとんど知られていない。著者は、保護観察対象者の犯罪誘発的ニーズを評価する評価手続きに焦点を当てることで、このギャップを埋めようとしている。これにより、知的障害を持つ保護観察対象者と関わる際の保護観察官の意思決定が明らかになると考えられる。
方法:この論文は定性的な方法に基づいています。イングランド北西部の保護観察官に対して、合計 6 回の半構造化詳細インタビューを実施しました。データは修正グラウンデッド・セオリー・アプローチを使用して分析されました。
調査結果:分析の過程で、知的障害を持つ保護観察対象者の特定、リスク評価活動中に保護観察官が知的障害をどのように文脈化するか、および監督の結果を決定する際の知的障害の役割という 3 つの主なテーマが浮かび上がりました。
この論文のデータは、保護観察所が地域社会の犯罪者のリスク評価と監督に用いる手続きが、有罪、意図、罪悪感に関する実証主義的な考えを助長していることを示唆している。その結果、知的障害のある犯罪者は保護観察所によってそのニーズが不正確に評価されるリスクがあり、この集団が不適切に管理、監督される可能性が増す。結論として、保護観察所が用いる評価ツールは、自己主張よりも管理と規律の手段を優先しているようで、知的障害のある犯罪者が刑事司法制度に引き込まれ、その制度を通じて処理されるリスクが大幅に増している。
免責事項: この要約は人工知能ツールを使用して翻訳されており、まだレビューまたは確認されていません