インデックス付き
- ユーロパブ
- Google スカラー
このページをシェアする
ジャーナルチラシ
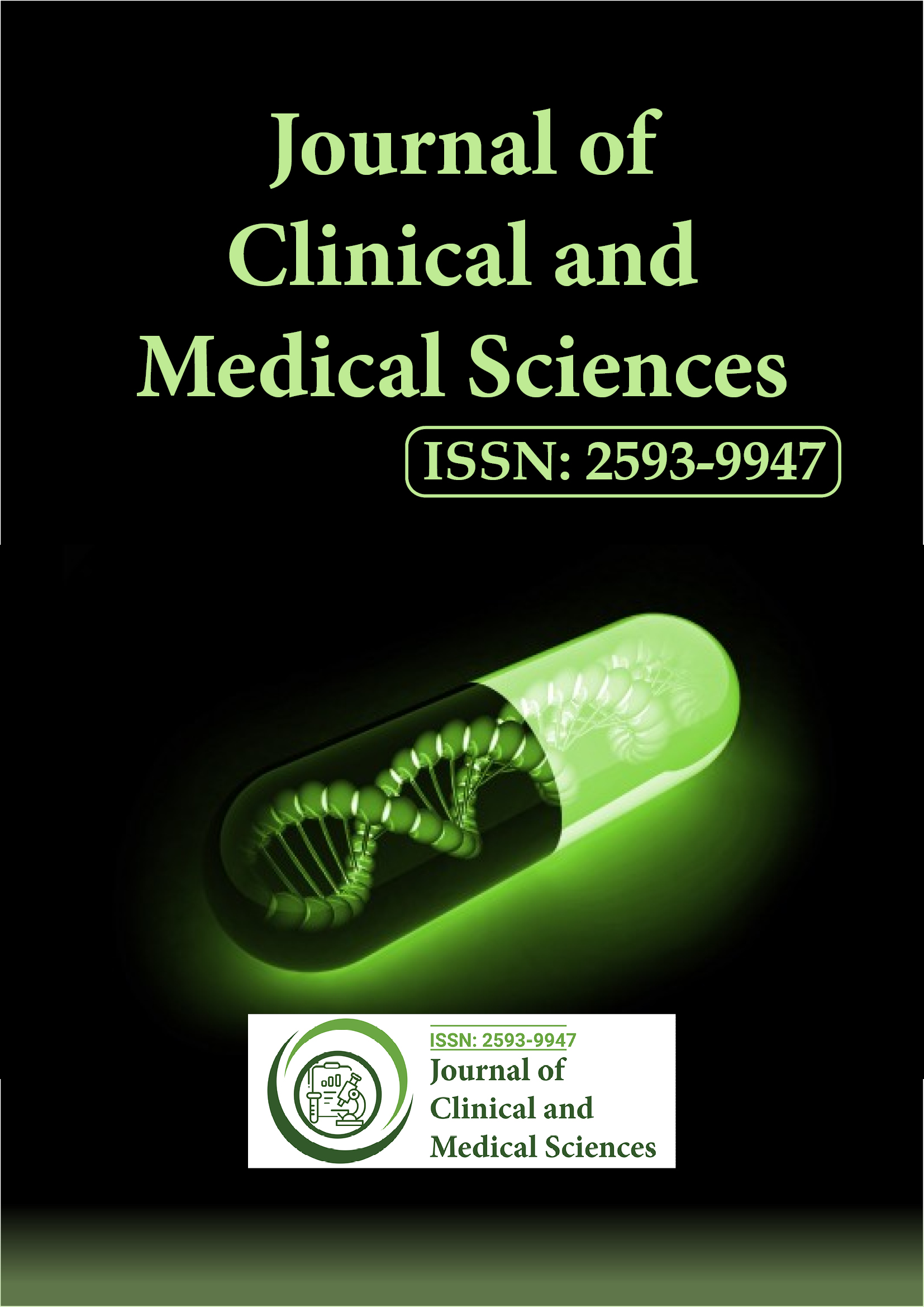
概要
神経組織と非神経組織におけるプログラニュリンとFRamidesがC. elegansの食事制限に関連した寿命とタンパク質恒常性に及ぼす役割
ディラワール・アフマド・ミール*、マシュー・コックス、ジョーダン・ホロックス、チェンシン・マー、アリック・ロジャース
食事制限(DR)は、アルツハイマー病や関連認知症などの神経変性疾患の根底にある、加齢に伴うタンパク質恒常性の喪失を軽減します。以前、私たちはC. elegansにおいて食事制限下で特定の FMRFamide 様神経ペプチド( FLP)遺伝子と神経保護成長因子プログラニュリン遺伝子prgn-1の翻訳効率の増加を観察しました。ここでは、標準および食事制限条件の両方で、 flp-5、flp-14、flp-15およびpgrn-1が寿命とタンパク質恒常性に及ぼす影響をテストしました。また、神経組織または非神経組織での発現に基づいて機能をテストし、区別しました。pgrn-1および flp 遺伝子の発現を神経組織で選択的に低下させたところ、実施した3つの実験のうち2つで、通常の摂食条件でもDRでも生存率に違いは見られませんでした。非神経組織におけるflp-14の発現低下は、 DR に特有ではない寿命の短縮を示しました。タンパク質恒常性に関しては、満腹の野生型動物と比較して耐熱性が向上したeat-2 遺伝子の変異による DR の遺伝子モデルは、 pgrn-1またはflp遺伝子のノックダウンに応じて耐熱性に変化がないことを示しました。最後に、神経特異的タンパク質毒性モデルで運動性への影響をテストし、pgrn-1およびflp遺伝子の神経ノックダウンにより、食事に関係なく幼少期の運動性が改善されることを発見しました。ただし、非神経組織でこれらの遺伝子をノックダウンした場合の結果はさまざまでした。flp -14を標的とする RNAi により、食事に関係なく成体 7 日目までに運動性が向上しました。興味深いことに、pgrn-1の非神経 RNAiにより標準給餌条件下での運動性が低下したのに対し、DR ではこの遺伝子のノックダウンで 7 日目 (中年期初期) までに運動性が向上しました。結果は、pgrn-1、flp-5、flp-14、およびflp-15 が、食事に関連した寿命の変化や全身のタンパク質恒常性において主要な役割を果たしていないことを示しています。ただし、ニューロンにおけるこれらの遺伝子の発現が低下すると、タンパク質毒性の神経特異的モデルにおいて幼少期の運動性が向上しますが、非ニューロン発現のノックダウンは、同じ条件下で中年期の運動性の向上がほとんどです。